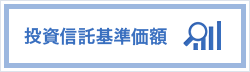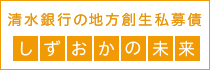1.誰でも利用できますか?
サービス利用方法について
1.以下の全ての条件を満たす方がお申込いただけます。
- 当行に口座(普通・当座)をお持ちの方
- 法人及び個人事業主の方
- インターネットに接続できるパソコン環境をお持ちの方
- Eメールアドレスをお持ちの方
- ファクシミリサービス以外のアンサーサービスご契約のない方(現在アンサー契約お申込の方は解約が必要となります)
- PCバンキングをご契約の方で、でんさいネットサービスのみを法人ダイレクトでご利用することができます。
2.複数口座があるが利用できますか?
2.代表口座にて1口座、代表口座以外に最大19口座までご登録いただけます。
3.複数の人数で利用することができますか?
3.最大20名までご利用いただけます。
4.複数の人数で利用する場合は利用権限は誰が管理するのですか?
4.マスターユーザーが行います。1契約1名のみマスターユーザーとして登録できます。
5.マスターユーザーとは何ですか?
5.本サービスの管理者(責任者)となります。契約内容の全業務がご利用になれます。
また自身を含む全ての利用者の権限設定ができます。
6.管理者ユーザーとは何ですか?
6.管理者ユーザーは、企業管理権限および利用者管理権限を持つ利用者のことを指します。
7.一般ユーザーとは何ですか?
7.本サービスの担当者となります。マスターユーザーまたは管理者ユーザーから与えられた利用権限に沿って本サービスをご利用いただけます。
8.一般ユーザー毎に利用できるサービスを限定することはできますか?
8.マスターユーザーまたは管理者ユーザーが、一般ユーザー毎に利用サービスを設定できます。変更・削除も随時可能です。
9.ご利用明細は発行されますか?
9.ご利用明細は発行されません。
10.海外からは利用できますか?
10.各国の法令・通信事情その他の事由により、全部または一部ご利用いただけない場合があります。
アンサーサービスからの切替について
1.現在、ファクシミリサービスを利用しているが併用して利用ができますか?
1.併用は可能です。手数料は別途必要です。
但し、法人ダイレクトの「入出金明細照会」にて、照会条件「期限で指定」を選択された場合、FAXサービスは出力されませんのでご注意ください。
2.アンサーサービスを利用しているが併用は可能ですか?
2.ファクシミリサービスは他のサービスと併用が可能です。
3.PCバンキングにて利用していた下記のデータを使用することはできますか?
- 基本サービスのデータ移行
- データ伝送のデータ移行
3.基本サービス(照会・振込振替サービス)のデータの移行は出来ません。
データ伝送サービスのデータの移行は可能です。
以下の手順となります。お客様ご自身で操作していただきます。
- 移行する新規振込データをオフィスバンクにて作成いたします。
(移行データ作成手順書参照:ご希望の方は取引店または、コールセンターにご請求ください) - 作成したデータをパソコンのデスクトップまたはFD等の媒体に取り込みます。
- 法人ダイレクトのデータ伝送に取り込みます。
※以下の点にご注意ください
- 手数料負担項目は引き継がれません。
- グループ分け機能は引き継がれません。
- 銀行支店情報が最新でない場合はエラーとなります。
- エラーリストが出力された場合、元データにて修正をしてから再登録してください。
- 振込先名(漢字)は移行されません。
- 銀行用のデータ(全銀ファイル)の仕様である必要があります。
お電話にて操作ご希望の方は、下記までご連絡ください
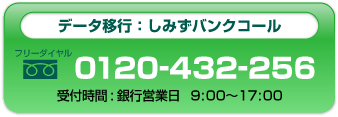
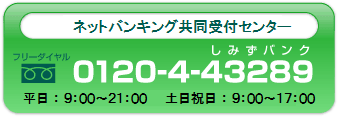
手数料について
1.月額基本手数料の引き落とし日はいつですか?領収書の発行はされますか?
1.月額1,650円(手数料含む)が翌月7日(銀行休業日の場合翌営業日)に代表口座より引落しとなります。
領収書は発行いたします。
2.データ伝送手数料はいくらですか?領収書は発行されますか?
2.総合振込、給与振込、口座振替、地方税は月額2,200円です。
入出金明細照会又は振込入金明細照会は月額3,300円です。
基本手数料1,650円と合算で引落しとなります。
領収書はまとめて1枚で発行されます。基本手数料と後納手数料の明細が記載されています。
3.手数料の優遇サービスはありますか?
3.手数料の優遇はありません。
基本サービスの申込月は、月額手数料が無料となります。
(ファクシミリサービス併用のご利用がない場合に限ります)
4.都度振込手数料は振込金額と別に引落しになりますか? 領収書は発行されますか?
4.振込手数料と振込金額は別々の引き落としとなります。
領収書は発行いたしません。
5.後納手数料の引き落とし日は、いつですか? 領収書は発行されますか?
5.後納手数料をお申し込みの場合、振込手数料と月額基本手数料は翌月7日に、別々の引き落としとなります。
でんさいネットサービスをご利用されている方は、別途でんさいの手数料が1ヶ月分まとめて翌月10日に引き落しとなります。
領収書は発行いたします。
6.でんさいの手数料の引き落しはどうなりますか?
6.1ヶ月分まとめて翌月10日に引き落しとなります。(でんさいとしての月額基本手数料はございません。)
領収書は発行いたします。
セキュリティーについて
1.インターネット上のセキュリティーが心配だが、改ざんなどの心配はありませんか?
1.世界標準的な暗号方式である128ビットSSL方式を採用しております。
24時間のアクセス監視を行うなど、安全面への配慮を行っています。
2.不正利用された場合の対応はどのようにすればよいですか?
PC/OS/ブラウザについて
1.利用できるOS/ブラウザは何でもよいですか?
1.128ビットSSL暗号化通信方に対応しているブラウザ゙が必要です。
動作環境につきましては、こちらをご覧ください。
2.Macの利用は可能ですか
2.対応しておりません。
3.社内LANでも利用できますか?
3.ご利用いただけない場合がありますので社内のネットワーク管理者にご確認ください
4.職場と自宅の両方の環境で利用できますか?
4.電子証明書方式にてセキュリティー対策を行っている為、証明書をダウンロードしているパソコンでしか利用できません。
他のパソコンで利用いただくためには、それぞれのパソコンに証明書をダウンロードしていただく必要があります。
マスターユーザーとして登録しているパソコンは1台のみとなります。
5.1台のパソコンで複数のユーザーが利用できますか? 複数の異なる契約が利用できますか?
5.複数のユーザー設定が可能です。(最大20名)
複数の異なる契約者での利用も可能です。
ログイン後、電子証明書の選択画面にて、該当する電子証明書を選択し、利用していただけます。
6.パソコンが壊れた、買い換えた、初期化した等の場合、他のパソコンを利用したいがどうしたらよいですか?
6.お取引店にて電子証明の再発行手続き(書面にて)が必要となります。
銀行にお申し出いただいてから翌営業日の午後に利用可能となります。
初期設定ID・パスワードについて
1.ログインIDとは何ですか?
1.サービス利用画面に入るための名前で、マスターユーザーが初回利用時に任意に名前で登録します。
他のお客さまが先に利用しているログインIDは登録できません。
ログインパスワード・確認用パスワードと同一の場合は登録ができません。
2.一般ユーザーを登録したいのですが、どうすればよいですか?
2.管理業務画面の「利用者管理」より登録いただけます。
3.ログインパスワード・確認用パスワードに有効期限がありますか?
3.90日となっています。
有効期限が切れた場合、パスワード変更を促す画面が表示されますので、変更してください。
4.ログインIDの変更はできますか?
4.ログインIDの変更はできません。
5.ログインIDを忘れてしまったのですが?
5.お取引窓口にお問い合わせください。
6.ログインパスワード・確認用パスワードを忘れてしまったのですが?
6.お取引店窓口にて、しみず法人ダイレクト申込書にご記入の上、「初回パスワード再発行」のお手続きをお願いします。
お取引店へご提出から2営業日後にご利用開始となります。
7.初期設定時に必要なものは何ですか?
7.あらかじめ、以下の情報・書類をご用意ください。
| お客さまで確認いただくもの | 銀行より交付されたもの |
|
|
電子証明書について
1.有効期限はどのくらいですか?
1.証明書発行日から366日です。
2.いつから更新可能ですか?
2.電子証明書有効期限40日前、10日前および当日に届くメールでの通知と、ログイン後の電子証明書更新選択画面およびトップ画面の「電子証明書更新」ボタンの表示により更新のご案内をします。
3.有効期限が切れてしまったが更新は可能ですか?
3.更新は可能です。ログイン画面の「証明書取得」ボタンを押し、ログインID・ログインパスワードを入力し、更新を行ってください。
ログインについて
1.「一定時間応答がないためお取引継続できません」の表示がされたのですが?
1.タイムアウトの状態です。再度ログインをしてください。
入出金明細照会サービスについて
1.入出金明細照会は何日間出力が出来ますか?
1.前々月の1日から当日分までの入出金明細がご照会いただけます。
また、ご利用開始以前の明細の照会はできません。
2.既に「最新」で照会した明細を再度照会ができますか?
2.「日付範囲で指定」を選択し、日付範囲を入力し、「照会」ボタンをクリックすると表示されます。
3.入出金明細の「日付範囲で指定」をしたが、残高照会の残高と相違しているのはなぜですか?
3.未照会の明細を照会の「期間で指定」照会をすると当日を含めた7営業日の明細が出力されます。
未照会の明細を照会の「期間で指定」照会後に取引があった場合、「日付範囲で指定」照会に反映されません。
未照会の明細を照会の「期間で指定」照会にてご確認ください。
4.照会できる件数に制限がありますか?
4.制限はありません。
15件を越えると次ページに表示されます。
5.ファクシミリサービスとの併用していますが、明細はどちらにも出力されますか?
5.法人ダイレクトにて取引明細照会を行った明細はFAXサービスの出力対象外となります。
6.入出金明細のダウンロードはできますか?
6.照会結果画面にて「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。
振込・振替サービスについて
1.予約振込をしたが、指定日当日、依頼内容照会確認したところ、「エラー」となっていましたがどうしてか?
1.振込が不成立となっております。振込指定日の朝、処理されるため、残高が不足である可能性があります。取引明細照会にて残高の確認をお願いします。
2.関連口座から振込資金を引き落とすことは可能ですか?
2.振込・振替サービスは代表口座・関連口座どちらからも引き落としが可能です。
3.振込(振替)2口座それぞれ1億ずつ引き落としたいが可能ですか?
3.可能です。
ご利用限度額は1口座あたり1日1億円です。但し、別途ご利用限度額変更のお手続きにより最大99億9999万円まで変更が可能となります。
4.他行宛ての振込で受取人名を入力したところ、「入力項目が誤っています」のエラーが表示されますが、どうすればよいのですか?
4.受取人名に入力できる文字数は半角30文字以内となります。
受取人名で入力できる文字は、以下の通りです。
- 半角カタカナ及び濁点(゛)半濁点(゜)
- 小文字のカタカナ(アイウエオヤユヨ)は大文字のカタカナで入力してください。
(例)ファンド → フアンド - 半角英数字大文字
- 半角記号9種類 ¥ 、 .( )‐/「 」
- 半角スペース
※次の文字は入力できませんのでご注意ください。
- ・ ― &
5.振込先が法人の場合どのように入力しますか?
5.以下のように略してご入力ください(実際は半角カナになります)
- 株式会社○○ → カ)○○
- ○○株式会社 → ○○(カ
- 有限会社○○ → ユ)○○
- ○○営業所 → ○○(エイ
- ○○出張所 → ○○(シユツ
- 医療法人○○ → イ)○○
- 社団法人 → シヤ)
- 学校法人 → ガク)
- 宗教法人 → シユウ)
- 社会福祉法人 → フク)
- 合名会社 → メ)
- 合資会社 → シ)
6.海外に送金・海外銀行の日本支店はできますか?
6.できません。全国銀行データ通信システムに加盟している国内の金融機関のみです。
7.振込の領収書は発行されますか?
7.振込の明細書・領収書は発行されません。
ブラウザ上での印刷は可能です。
メニューバー「ファイル」の中の「印刷」を選択してください。
8.振込依頼人名は変更ができますか?
8.任意に入力すれば変更は可能です
9.入金先口座はいくつまで登録できますか?
9.15,000件まで登録が可能です。検索条件を入力し検索することができます。
10.振込み先口座番号等の入力で正当な口座番号、受取人名を相違すると、入力時にエラーとなりますか?
10.口座番号が相違している場合は、入力時にエラーとなります。必ず正当受取人名を確認してください。
※ご入力内容に誤りがあった場合、受取人様に振込入金されません。
振込の訂正・取消の場合取引店窓口にて手続きをとっていただきます。ご了承ください。
11.振込振替を取り消ししたい場合どうすればよいですか?
11.当日扱いの取り消しはできません。
お取引店窓口にて訂正・組戻手続きが必要となり、別途手数料もかかります。
※翌日扱いは「依頼内容照会・取消」にて、指定日前日まで取消が可能です。
12.依頼した振込振替の記録は何日間照会できますか?
12.振込振替履歴は90営業日、詳細が確認できる画面は7営業日となっております
事前登録方式について
1.事前登録方式の申込方法を教えてください。
1.予め書面でのお申込みが必要となります。
申込書「しみずアンサー振込・振替サービス入金指定口座申込書」は弊行ホームページ、
法人のお客さま>事業合理化>しみず法人ダイレクト>ご利用ガイド>各種申請書類より印刷していただくほか、お取引店窓口でお受取りください。
2.振込先の口座は、最大何件まで登録できますか?
2.最大999件まで登録できます。(受取人番号は「001」から「999」まで登録可能です)
3.口座毎(代表口座、関連口座)に振込先の口座情報を登録する必要がありますか?
3.口座毎に登録する必要があります。
申込書のお支払い指定口座に「代表口座」をご記入ください。登録した振込先の口座は、代表口座と関連口座でご利用いただけます。
4.代表口座から関連口座(または関連口座から代表口座)に振替取引を行う場合は、どのような手続きが必要ですか?
4.申込書のお支払い指定口座に「代表口座」をご記入した後
- 「代表口座→関連口座」をご利用の場合は、ご入金指定口座に「関連口座」をご記入ください。
- 「関連口座→代表口座」をご利用の場合は、ご入金指定口座に「代表口座」をご記入ください。
5.登録した振込先の口座は、しみず法人ダイレクトの画面上で確認することができますか?
5.登録した振込先の口座情報は、しみず法人ダイレクトの画面上ではご確認いただくことはできません。お手数をおかけしますが、「しみずアンサー振込・振替サービス入金指定口座申込書」の控え(コピー)をご確認ください。
6.事前登録方式の振込振替操作方法を教えてください。
6.「振込振替」メニューより、「振込データの新規作成」ボタンをクリックし「支払口座」を選択した後「振込先口座指定方式」画面が表示されます。
事前登録方式は、「受取人番号を指定」ボタンを選択することでご利用いただけます。
7.「振込先口座指定方式選択画面」に「受取人番号を指定」のボタンが表示されません。
7.事前登録方式をご利用する前に、「管理業務」メニューから「利用者管理」画面にて権限設定を行う必要があります。設定方法の詳細についてはこちら
※サービス利用権限の設定変更操作は、「マスターユーザ」または「管理者ユーザ」のみ可能です。トランザクション認証に関するご質問
1.トランザクション認証とは何ですか。
1.トランザクション認証とは、取引(トランザクション)の内容が、通信の途中で改ざんされていないことを確認し、認証を行う方法です。
口座番号や金額等の情報を暗号化した二次元コードを専用のカメラ付きトークンで読み取り、トークン画面に表示された取引内容を確認することで不正取引を防止します。
2.カメラ付きトークン(トランザクション認証用トークン)とは何ですか。
2.パスワードを生成する専用機器です。
取引画面に表示される二次元コードをカメラで読み取ることで、トークン画面に取引内容やトランザクション認証番号(取引内容に基づいて生成されたワンタイムパスワード)が表示されます。
3.シリアル番号とは何ですか。
3.トークン裏⾯の番号(2桁、7桁、1桁)です。シリアル番号は、トランザクション認証利用開始登録で使⽤します。
4.カメラ付きトークンに有効期限はありますか。
4.電池交換可能になっていますので、有効期限はありません。
電池(単4電池3本)を交換することで、長期間のご利用が可能です。なお交換⽤電池はお客さまにてご負担ください。
5.なぜトランザクション認証を使うのですか。
5.インターネットバンキングの不正取引の手口は日々巧妙化しており、近年では「振込先口座情報を改ざん」する手口が確認されています。トランザクション認証は、お客さまが行った振込等の取引内容が、ウィルス等により改ざんされていないことを確認することで不正取引を防止します。
6.トランザクション認証を利用することで不正取引に遭う可能性はないですか。
6.トランザクション認証とは、取引の内容が、通信の途中で改ざんされていないことを確認し、認証を行う方法です。
お客さまのパソコンのセキュリティを⾼めるものではありません。安全にご利⽤いただくために、お客さま⾃⾝のご利⽤環境においても、OS・ブラウザの最新化、ウィルス対策ソフトの最新化やウィルスチェックの徹底等のセキュリティ対策を実施いただきますようお願いいたします。
7.トランザクション認証を利用するにはどうすれば良いですか。
7.申込⼿続きは必要ありません。しみず法⼈ダイレクトをご契約いただいているすべてのお客さまがご利⽤いただけます。
8.トランザクション認証の利用をやめたい。
8.しみず法⼈ダイレクトをご契約のすべてのお客さまにご利⽤をお願いしています。
お客さまには⼤変ご不便をおかけしますが、インターネットバンキングを安⼼してご利⽤いただくために必要なセキュリティ対策となりますので、何卒ご理解をお願いします。
9.トランザクション認証はどのような取引で使用しますか。
9.トランザクション認証が必要となる取引は、以下のとおりです。
- 振込振替(都度指定⽅式)
- 税⾦・各種料⾦の払込み(⺠間収納機関のみ)
- 総合振込・給与・賞与振込
- 振込先の管理
- 管理業務(利⽤者登録・変更)
- トークンの失効
10.トランザクション認証の利用手数料はかかりますか。
10.トランザクション認証に係る初回発⾏⼿数料、⽉額⼿数料は無料です。
11.複数ユーザ(マスタ・管理者・一般)でカメラ付きトークンを共有することはできますか。
11.可能です。各ユーザがトランザクション認証利⽤開始登録画⾯で、同⼀のシリアル番号を選択することでカメラ付きトークンを共有することができます。
12.1ユーザで複数のカメラ付きトークンを利用することはできますか。
12.利⽤できません。1ユーザで利⽤できるカメラ付きトークンは1個です。
13.本社・支社など複数拠点で使用したい場合、カメラ付きトークンの追加申込はできますか。
13.可能です。書⾯による⼿続きが必要となりますので、お取引店窓⼝にご相談ください。
なお、追加発⾏を⾏う場合、発⾏⼿数料として1個につき2,200円(税込)がかかります。追加分のカメラ付きトークンは郵送いたします。お⼿元に届くまで⽇数をいただきますのでご了承ください。
14.複数の会社を持っていますが、カメラ付きトークンを共有することはできますか。
14.1つのカメラ付きトークンを複数の会社で共有することはできません。
15.利⽤開始登録を⾏わないとサービスが利⽤できなくなりますか。
15.トランザクション認証が必要となる取引はご利⽤できないため、すみやかに利⽤開始登録をお済ませください。
16.利⽤開始登録画⾯が表⽰されない。
16.トランザクション認証が必要な取引の権限がないユーザは、ログインした後の「トランザクション認証利⽤開始登録」画⾯が表⽰されません。
17.しみず法⼈ダイレクト新規申込後、カメラ付きトークンはどのくらいで届きますか。
17.お申込から約1週間程度で「ご利⽤開始のお知らせ」と⼀緒にカメラ付きトークン1個を送付いたします。しみず法⼈ダイレクトをご利⽤いただく際に必要となりますので、⼤切に管理してください。
18.カメラ付きトークンを紛失した場合はどうすれば良いですか。
18.カメラ付きトークンを紛失された場合は、すぐにお取引店にご連絡ください。
カメラ付きトークンの再発⾏は、お取引店での⼿続きが必要となります。なお、再発⾏⼿数料として、1個につき2,200円(税込)がかかります。
紛失したカメラ付きトークンを複数ユーザで使⽤している場合は、再発⾏⼿続き後、マスタユーザの⽅が別ユーザ分のトークン失効を⾏ってください。(管理者メニュー内の利⽤者管理ボタンから「トランザクション認証のトークン失効」をクリックすると、該当ユーザのトークンが失効できます)
19.トランザクション認証番号の⼊⼒を何回か間違えたため、利⽤できなくなってしまった。
19.トランザクション認証番号(取引内容に基づいて生成されたワンタイムパスワード)を⼀定回数間違えて⼊⼒すると、不正取引防⽌のためトランザクション認証が必要な取引が⾏えなくなります。
利⽤停⽌状態を解除するには、別のシリアル番号のカメラ付きトークンを使⽤するマスタユーザまたは管理者ユーザの⽅が「トランザクション認証の利⽤停⽌解除」操作を⾏ってください。別のシリアル番号のカメラ付きトークンをお持ちでない場合は、お取引店でワンタイムパスワード利⽤停⽌解除の⼿続きを⾏ってください。
税金各種料金払込ペイジーについて
1.税金・各種料金払込みサービスとは何ですか?
1.ペイジーマークの記載された税金(国税)のお支払いができるサービスです。
![]()
2.取り扱いできる税金は何がありますか?
2.下記の「当行でご利用可能な収納機関一覧」をご参照ください。
※![]() 「Pay-easy(ペイジー)」マークのある払込書などに記載されている「収納機関番号」「納付区分」「確認番号」の入力が必要となります。
「Pay-easy(ペイジー)」マークのある払込書などに記載されている「収納機関番号」「納付区分」「確認番号」の入力が必要となります。
※記載がない場合、ご利用いただけません。
3.「Pay-easy(ペイジー)」とは何ですか?
3.日本マルチペイントネットワーク運営機構が提供する「収納サービス」等の周知・普及を図る為の愛称です。
![]()
◇参考HP
http://www.pay‐easy.jp/
4.関連口座からの引き落としは可能ですか?
4.代表口座・関連口座ともに可能です。
5.民間企業(保険料等)の支払いは可能ですか?
5.下記の「当行でご利用可能な収納機関一覧」をご参照ください。
◇当行でご利用可能な収納機関一覧
6.領収書は発行されますか?
6.発行いたしません。
収納機関へお問い合わせください。
7.間違った金額を払い込むことはありませんか?
7.ご入力いただいた番号で検索し、画面に表示されますので、請求書と同一であるかを確認後お支払いいただきます。
8.払込したかどうかの確認はどのようにすればよいですか?
8.口座から支払いされているか確認してください。また「依頼内容照会・取消」にて90日間閲覧が可能です。
9.予約にて手続きはできますか
9.予約扱いはできません。当日のみの取扱となります。
10.手続き完了後に取り消すことはできますか
10.一度操作したペイジーの支払いは取消することが出来ません。
データ伝送サービスについて
1.申込手続きはどのようにしたらよいですか?
どれくらいのスケジュールで使えるようになりますか?
1.お取引店にて書面でのお申込みとなります。
お申込の流れは以下の通りです。
- 法人ダイレクト申込書にご署名ご捺印をいただき取扱店窓口にてお申出いただきます。
- 1週間程で、契約書2部と口座振替依頼書をお渡し致します。契約書の2部と口座振替依頼書にご署名・ご捺印いただき、取引店にご提出ください。
- 契約書の1部を取引店から受取後、1週間程お待ちいただきます。
- 利用開始となりましたら、お取引店よりお電話にて開始連絡をいたします。
- マスタユーザまたは管理者ユーザの方は、法人ダイレクトサービスにログインしていただき、管理業務メニューの「利用者管理」から「利用者情報の管理」を選択し、データ伝送の操作を行うユーザのサービス利用権限を変更してください。
- サービス利用権限を変更したユーザは、ログイン後、トップページ画面にデータ伝送メニューが追加されていることをご確認ください。
※変更内容の反映には、ログアウト後に再ログインが必要です。
2.どのようなサービスですか?
2.お振込などを一括して送信できます。下記の表をご参照ください。
| 総合振込 | お振込データを一括して送信ができます。 |
|---|---|
| 給与振込 | 給与データを一括で送信できます。 |
| 口座振替 | 代金回収等による口座振替を一括で請求ができます。 |
| 地方税 | 市区町村税(住民税)の納付ができます。 |
3.振込の限度は一日いくらまでですか?
3.総振・給振は最大9億9千百万円まで任意に申し込みが可能です。書面にてお申出いただきます。
4.承認時限とは何ですか?
4.データを作成し、承認まで完了する期限です。
5.承認時限を過ぎるとどうなりますか?
5.〈総合振込・当行宛給与振込の場合〉
ご指定日の前営業日正午(12:00)を過ぎますと送信はできません。お取引店にご連絡をお願いします。
〈他行宛給与振込の場合〉
ご指定日の3営業日正午(12:00)を過ぎますと、給与でのデータ送信はできません。前営業日前の正午(12:00)まで振込扱いで送信可能ですが、所定の手数料がかかります。
6.承認済みのデータを修正・取消ができますか?
6.承認済みのデータは承認実行から最初に到来する当行の処理実行時間(銀行営業日の9:00、11:00、13:00、14:00、15:30)内であれば、画面操作で取消することができます。
承認取消を行った取引は、修正して再度承認依頼をすることでができます。
<取消の画面操作>
データ伝送メニューの「総合振込」「給与・賞与振込」「口座振替」「地方税納付」業務から「承認済みデータの承認取消」の操作で取消を行うことができます。
当行の処理実行時間経過後、画面操作で取消できない取引は、以下の取消可能時限内であれば、お取引店へ電話連絡していただき、書面による手続きを行うことで取消することができます。
| データの種類 | 取消可能時限 |
|---|---|
| 総合振込 | 振込指定日の1営業日前16時まで |
| 給与・賞与振込 | 振込指定日の3営業日前16時まで |
| 口座振替 | 振替日の2営業日前16時まで |
| 地方税納付 | 納付指定日の5営業日前16時まで |
※取消可能時限経過後は取消できません。
7.総合振込、給与振込、賞与振込、口座振替、地方税納付の各取引で受付可能なファイルフォーマットを教えてください。
8.会計ソフトや給与計算ソフトなどで作成したデータを送信することは可能ですか?
8.全銀協規定のファイル形式、またはCSVファイル形式であれば受付が可能です。
総給振の受付・送信方法は「オンラインマニュアル」の「振込ファイルの受付」を参照してください。
9.振込時に依頼人名の変更ができますか?
9.依頼人名欄に変更するご名義等をご入力してください。
10.EDI情報とは何ですか?
10.電子データ交換の事で、企業間の商取引に関する情報を標準的な書式に統一して、そのデータを電子的に交換するシステムの事です。
でんさいネットサービスについて
1.手形はなくなるのですか?
1.手形がなくなるわけではありません。
「でんさい」は手形債権や売掛債権の課題を克服し、事業者さまの資金決済の効率化と資金調達の円滑化を図る目的で創られた、新しい金銭債権でございます。 資金決済手段の選択は、最終的には事業者さまの判断に委ねられます。
2.「でんさいネット」の「でんさい」を取り扱う金融機関はどこですか?
2.銀行、信用金庫、信用組合、農林系統金融機関(農協等)、商工中金など、全国の金融機関です。
取り扱いの金融機関一覧は、でんさいネットのホームページで確認することができます。
3.「でんさい」で取引するメリットは、何ですか? <支払企業(債務者)の場合>
3.以下のメリットがございます。
- ペーパーレス
- 手形の発行、振込の準備など、支払に関する面倒な事務負担が軽減されます。
- 手形の搬送コストが削減されます。
- 印紙税が課税されません。
- 手形と異なり、印紙税は課税されません。
- 支払手段の一本化で効率的
- 手形、振込、一括決済など、複数の支払手段を一本化することも可能となり、効率化が図れます。
4.「でんさい」で取引するメリットは、何ですか? <納入企業(債権者)の場合>
4.以下のメリットがございます。
- ペーパーレス
- 紛失や盗難の心配がなくなります。
- 厳重に保管、管理する必要がなくなりますので、無駄な管理コストを削減することができます。
- 分割可能
- 手形とは異なり、1つの債権を必要な分だけ分割して譲渡や割引をすることができます。
ただし、分割可能な金額は1万円以上となります。
- 手形とは異なり、1つの債権を必要な分だけ分割して譲渡や割引をすることができます。
- 期日に自動入金
- 支払期日になると取引銀行の口座に自動的に入金されますので、面倒な取立手続きは不要です。
- 債権を有効活用
- 「でんさい」は流通性の高い債権です。「でんさい」であれば、これまで資金繰りのために利用できなかった債権も、譲渡や割引が可能になり、無駄なく有効に活用することができます。
5.期日振込との違いを教えてください。
5.「でんさい」は手形と類似の制度設計となっており、(1)支払期日に債務者口座から債権者口座へ自動送金される点、(2)期日前にでんさいを譲渡等することで、相手方から資金を受け取ることが可能な点が期日振込と大きく異なります。
6.手形と同じ様に割引や譲渡することはできますか?
6.可能です。
「でんさい」独自の便利な機能として、「分割」して割引や譲渡をすることも可能です。
分割の最低債権金額は1万円となります。ただし、1万円以上を分割した結果、原債権(手形に残る債権)が1万円未満になることは可能です。
7.会計処理上、どの様な取り扱いになりますか?
7.平成21年4月に企業会計基準委員会より「電子記録債権に係る会計処理及び表示についての実務上の取り扱い」が公表され、一般的な会計について指針が示されております。
原則、「支払手形/受取手形」に準じて「電子記録債務/電子記録債権」と区分することとなっています。
※会計処理に係る実際のご判断は、貴社ご担当の会計士とご相談いただきますようお願いします。
(事例) 債務者Aが債権者Bから商品100万円を購入
(1)債務者(A)
- ① 商品100万円の売買
-
(借)仕 入 100万円 (貸)買掛金 100万円 - ② 発生記録請求により、電子記録債権に係る債務100万円が発生
-
(借)買掛金 100万円 (貸)電子記録債務 100万円 - ③‐1.
債権者が譲渡記録により電子記録債権を現金95万円と引換えに譲渡した場合 -
仕訳なし - ③‐2.
債権者が譲渡記録により電子記録債権を買掛金100万円と引換えに譲渡した場合 -
仕訳なし - ④ 債務100万円の決済
-
(借)電子記録債務 100万円 (貸)現金 100万円
- ① 商品100万円の売買
-
(借)売掛金 100万円 (貸)売上 100万円 - ③ 発生記録請求により、電子記録債権100万円が発生した場合
-
(借)電子記録債権 100万円 (貸)売掛金 100万円 - ③‐1.
譲渡記録により電子記録債権を現金95万円と引換えに譲渡した場合 -
(借)現金
電子記録債権売却損95万円
5万円(貸)電子記録債権 100万円 - ③‐2.
譲渡記録により電子記録債権を買掛金100万円と引換えに譲渡した場合 -
(借)買掛金 100万円 (貸)電子記録債権 100万円 - ③‐3.債権100万円が決済された場合
-
(借)現金 100万円 (貸)電子記録債権 100万円
8.商品代金としてでんさいを受け取る場合には、領収書を発行する必要はありますか?
8.領収書を発行するか否かは当事者間の取り決め次第であり、必ずしも領収書を発行する必要はありません。
領収書を発行しない場合、記録事項の開示で対応することが考えられます。ただし、譲渡記録ででんさいを受け取り、その後、受け取ったでんさいを他の利用者に譲渡したケースでは、譲渡記録が閲覧できなくなる可能性がある点、ご留意ください。
9.商品代金としてでんさいを受け取る際に領収書を発行した場合、当該領収書に収入印紙を貼付すべきでしょうか?
9.商品代金としてでんさいを受け取る際に領収書を発行した場合には、当該領収書に収入印紙を貼付する必要はありません。
商品代金として受け取るでんさいは、電子記録債権であり、金銭や有価証券ではないため、でんさいを受け取る際に領収書を発行した場合であっても、当該領収書は印紙税法上の課税文書に該当しないためです。
なお、でんさいを受け取る際に発行する領収書であっても、「上記金額をでんさいで受領いたしました。」などでんさいで受け取った旨の記載がない場合には、印紙税法上の課税文書(第17号の1文書)に該当します。
10.サービス利用可能日および利用可能時間を教えてください。
10.でんさいネットのオンライン時間は、7:00~24:00となっていますが、当行の取り扱い時間は以下の通りです。
【 平 日 】 8:00~21:00
【銀行休業日】 9:00~19:00
- 12月31日から1月3日、5月3日から5日、および毎月第2土曜日の終日はご利用いただけません。
11.しみず法人ダイレクトを契約していないが「でんさい」の取引を行うことはできますか?
11.でんさいネットは、電子記録債権の発生や譲渡、受取の取引がインターネット上で利用することができます。事務負担や管理コストの軽減になりますので、しみず法人ダイレクトにご契約して、でんさいネットサービスを利用されることをお勧めします。
12.複数の金融機関で、でんさいネットを利用することはできますか?
12.利用できます。但し、具体的な方法は各窓口金融機関によって異なる場合があります。利用申込は窓口金融機関ごとに行っていただく必要があります。
13.取引先がでんさいネットを利用していませんが、でんさいで支払うことはできますか?
13.取引先がでんさいネットを利用していない場合は、でんさいで支払うことはできません。
でんさいで支払いをするためには、債務者だけでなく、取引先(債権者、譲受人等)も利用者になる必要があります。
14.当社と取引先とで取引金融機関が異なりますが、でんさいを発生させることはできますか?
14.発生させることができます。
貴社とお取引先の取引金融機関が異なる場合であっても、いずれの金融機関もでんさいネットに加盟して、かつ利用者(貴社およびお取引先)―窓口金融機関―でんさいネットの三者間で「利用契約」を締結していれば、でんさいを発生させることは可能です。(でんさいネットに加盟している金融機関一覧は、でんさいネットのホームページで確認することができます)
15.他の記録機関で発生させた電子記録債権を、でんさいネットで利用することはできますか?
15.「でんさいネット」と提携している記録機関で発行された電子記録債権を「でんさいネット」に移動し、でんさい割引等を利用することができます。
利用するためには、債権者の方が債務者の承諾を得て、提携記録機関に対して記録機関変更の手続をする必要があります。
16.基本手数料、1件あたりの手数料はどうなりますか?
16.でんさいを利用するための月間の基本手数料はございません。
「でんさい」の発生記録請求や譲渡記録請求(分割譲渡含む)等のお取引には1件あたり所定の手数料が必要となります。詳細は、手数料一覧をご覧ください。
17.取引先から「でんさい」で支払われた時は、手数料はかかりますか?
17.入金時に決済手数料として手数料が必要となります。
18.でんさいネットサービスにはどのようにアクセスしますか?
18.当行のホームページ(https://www.shimizubank.co.jp/)から『しみず法人ダイレクト』にアクセスしてください。
アカウントアクセス画面[BPT001]が表示されますので、画面左側の「電子記録債権メニューへ」ボタンをクリックしますと、でんさいネットサービスのトップ画面が表示されます。
19.「利用者番号」とは何ですか?
19.利用者を特定するためにでんさいネットが付与する9桁の番号で、でんさいをご利用の際に必要となります。
利用者番号は、1法人(1個人事業主)につき1つとなります。
20.利用者に対して「利用者番号一覧」が開示されますか?
20.利用者情報保護の観点から、利用者に対して、「利用者番号一覧」は開示されません。
21.「記録番号」とは何ですか?
21.電子記録の請求など、「でんさい」をご利用の際に必要となる番号です。
債務者(当該「でんさい」を発生させた支払企業)の利用者番号9桁と「でんさい」の固有の番号11桁の合計20桁が記録番号となっております。
22.債権の発生記録請求(債務者請求)とは、何ですか?
22.債務者として電子記録債権の発生を請求することです。
23.債務者からでんさいを発生させる手続を教えてください。
23.債務者からでんさいを発生させる手続(債務者請求方式)は、以下のとおりです。
- 債務者は、窓口金融機関を通じて発生記録請求を行います
- でんさいネットは、1.の請求を受け、発生記録を行います(でんさいの発生)。
通知を受けた債権者は、でんさいの内容を確認し、相違がある場合は、電子記録の日を含めて5銀行営業日以内であれば、単独でその発生記録を取り消すことが可能です。
24.債権発生請求(債務者請求)の取消しはできますか? 【債務者が取消す場合】
24.債権発生後に債務者側から取り消すことはできません。ただし、予約中であれば取消しが可能です。
【債権発生後の対応方法】
変更記録請求で債権そのものを削除することは可能です。
但し、債権者の同意(承認)が必要です。債権者以外に利害関係者がいる場合には、全員の書面による承諾が必要です。
25.債権発生請求(債務者請求)の取消しはできますか?【債権者が取消す場合】
25.受領した債権内容に異議がある場合は、発生記録の取消しが可能です。
債権者からの取消は発生予約中の債権と、通知日から5銀行営業日以内の債権について可能です。
5銀行営業日経過後は変更記録請求で債権そのものを削除することは可能です。
但し、債務者の承諾が必要となります。
26.譲渡制限有無は、どちらを選択すればよいですか?
26.債権の譲渡先を金融機関に限定したい時には「有」を選択してください。
「有」を選択した場合、譲受人は当該債権を一般企業宛に譲渡できなくなります。
27.でんさいの支払期日に何か制限はありますか?
27.発生日(注)から起算して7銀行営業日以内の日付、または発生日の10年後の応当日の翌日以降の日付を支払期日とすることはできません。
(注)発生日が銀行休業日の場合は、翌銀行営業日
例 2013年2月18日に発生させた場合
最短支払期日 2013年2月27日
最長支払期日 2023年2月18日
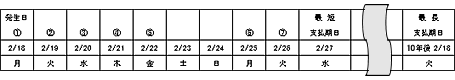
28.でんさいの支払期日等を変更することはできますか?
28.支払期日の7銀行営業日以前の日までに全ての利害関係者の承諾を得られるのであれば、でんさいの支払期日を変更することは可能です。
債権金額や支払期日など、利用者属性以外の記録を変更する場合は、利害関係者の承諾が必要です。変更記録の請求方法および利害関係者の承諾を得る方法は、変更対象となるでんさいの状態によって違いがあります。
29.でんさいの支払期日等を変更する手続を教えてください。
29.利害関係者の人数により、以下のとおり手続方法が異なります。
具体的な手続については、お取引店にお問い合わせください。
- 利害関係者が債務者と債権者しかいない状態(譲渡記録や保証記録等が行われる前)の場合、一方が変更記録請求を行い、5銀行営業日以内に相手方の承諾を得ることが必要です。
- 利害関係者が3名以上いる状態(譲渡記録や保証記録等が行われた後)の場合、利害関係者全員の書面による変更記録の請求が必要です。
30.債権の発生記録請求(債権者請求)とは、何ですか?
30.債権者として電子記録債権の発生を請求することです。
発生請求を行った後、相手方に承諾の依頼を行います。相手方から承諾を得ると債権者請求が成立します。なお、債権者請求の利用には債権者側だけでなく、債務者側も債権者請求を利用可能であることが必要になりますのでご注意ください。
31.債権者からでんさいを発生させる手続を教えてください。
31.債権者からでんさいを発生させる手続(債権者請求方式)は以下のとおりです。
窓口金融機関および債務者の状況により取扱可否が異なりますので、お取引店および債務者にお問い合わせください。
- 債権者は、窓口金融機関を通じて発生記録請求を行います。
- でんさいネットは、窓口金融機関を通じて、債務者に対して請求内容を通知するとともに、請求の承諾依頼通知を行います。
- 債務者は、2の通知を受けて請求内容を確認する。債務者がでんさいネットが2の通知を発した日を含め5銀行営業日以内に承諾した場合、でんさいが発生します。
債務者が否認した場合または上記期日内に回答をしなかった場合、でんさいは発生しません。
32.振出日(電子記録年月日)には当日または未来日付を入力することができますか?
32.当日から1ヶ月先までの予約が可能です。
尚、未来日付を入力した場合は予約請求となり、入力した日付が債権の発生日になります。- 債権の発生日はでんさいネットの取引画面上の振出日(電子記録年月日)と同じです。
33.債権の発生日(振出日)の期限である「1ヶ月後の応答日まで」は、具体的にいつをさしますか?
33.翌月の同日をさします。
月末の場合は、翌月の月末の日付となります。- 例:
-
2/27の1ヶ月後の応答日は3/27
2/29の1ヶ月後の応答日は3/31(※閏年の場合。月末のため日付が補正されます)
3/31の1ヶ月後の応答日は4/30(月末のため日付が補正されます)
34.支払期日として土日祝日など銀行営業日以外の日を指定して発生記録を請求した場合には、どのような取扱いになりますか?
34.翌銀行営業日を支払期日とする発生記録の請求があったものとして取り扱います。
35.保有する債権を譲渡することはできますか?
35.可能です。
譲渡記録請求は原則として、譲受人(ゆずりうけにん)になる利用者を債権者とし、譲渡人を保証人となります。
36.債権を分割して一部譲渡することはできますか?
36.可能です。手形にはない、電子記録債権特有の大きなメリットです。
債権を譲渡する場合、全額譲渡と債権を分割して行う一部譲渡が可能です。
分割件数に上限はありませんが、分割する1債権の金額は1万円以上となります。
37.譲渡日(電子記録年月日)は当日または未来日付を入力することができますか?
37.可能です。
なお、未来日付を入力した場合は予約請求となり、実際に債権が譲渡される日付は入力した譲渡日(電子記録年月日)となります。
38.未来日付の発生予定債権の譲渡予約はできますか?
38.可能です。ただし、2回目の譲渡予約はできませんのでご注意ください。
| <例> | 発生予定債権 | → | 1回目譲渡予約(可) | → | 2回目譲渡予約(不可) |
| (A社→B社) | → | (B社→C社…〇) | → | (C社→D社…×) |
なお、譲渡予約済みの債権は発生取消を行うことができません。
譲渡予約を取り消した場合は、発生予約も取り消すことができます。
39.譲渡回数に制限はありますか?
39.ありません。
また、電子記録債権のうち、必要な金額だけ分割して他の利用者に譲渡できます。
40.分割譲渡の最低債権金額に制限はありますか?
40.最低債権金額は1万円です。
なお、原債権記録(債権を分割譲渡された残りの債権)の金額は1万円未満になっても構いません。
41.譲渡記録日から5営業日を経過した後、譲渡請求を取消したい場合どうすればよいですか?
41.お客様の操作では譲渡の取消しができません。書面でのお手続きが必要になります。
手続き方法及び必要書類につきましては、お手数ですがお取引店にお問い合わせ頂くようお願い致します。
42.分割譲渡の予約を行いました。残った分割債権を譲渡するには、どうしたらよいですか?
42.残った債権を(全部・一部)譲渡するには、先の分割譲渡の譲渡日より、後の日付を譲渡日にしなければ譲渡できません。
43.債権の一括請求(一括記録請求)とは、何ですか?
43.一括して(まとめて)記録請求を行うことができる機能です。
一括記録請求が可能な記録請求は、発生記録、譲渡記録(分割記録含む)です。それぞれの記録請求ごとに複数の請求を一括して行うことができます。
担当者は、複数発生記録請求や複数譲渡記録請求を行うか、または当行が提供します「一括請求Assist」のソフトで作成したデータをアップロードして仮登録を行い、承認者が仮登録を承認することで、一括記録請求が完了します。
44.「変更記録請求」で可能な操作は、何ですか?
44.「支払期日」、「債権金額」、「譲渡制限有無」の変更または、債権を削除することが可能です。
但し、相手方の承諾が必要となります。
45.どの電子記録債権でも変更記録請求ができますか?
45.インターネットバンキング(当行の場合は法人ダイレクト経由)で変更記録請求が可能なのは、譲渡記録や保証記録等がない発生記録のみの電子記録債権です。
46.変更記録請求は、債権者からも債務者からもできますか?
46.可能です。
変更記録請求は、対象債権の債権者、もしくは、債務者から請求が可能です。
47.変更記録請求ができる期間は決まっていますか?
47.担当者による変更記録請求操作とその後の承認者による承認操作が、債権の支払期日の7銀行営業日前までに完了していることが必要になります。
48.「保証記録請求」とは、何ですか?
48.債権者が保有している電子記録債権に保証人を追加することができます。
「保証記録」は債権の譲渡を伴わない単独の保証記録を依頼し、相手方(保証人となる方)の承諾が必要となります。
49.融資、譲渡担保申込とは、何ですか?
49.「割引」または「譲渡担保」の申込を行うことができます。
「割引申込」ボタン、または「譲渡担保申込」ボタンより申込操作が可能です。
- 当行所定の審査を行った後に、ご利用いただける機能となります。
50.希望日として指定可能な範囲を知りたいのですが?
50.申込日(15:00以降は翌営業日)を含めた3銀行営業日後から当日の30銀行営業日後までの範囲となります。(希望入力日は銀行営業日のみ)
51.でんさいの内容の開示手続について教えてください。
51.通常開示はインターネットバンキング(当行の場合は法人ダイレクト経由)もしくは書面など、窓口金融機関の定める方法で手続いただき、特例開示は「特例開示請求書」を窓口金融機関へ提出いただく方法で手続いただくことになります。
52.「通常開示」と「特例開示」の違いについて教えてください。
52.「通常開示」とは、自らが債権者、債務者、および電子記録保証人であるでんさいの情報および記録請求に当たり提供した情報を開示するものです。
「特別開示」とは、通常開示の対象外となるでんさいの内容および記録請求に当たり提供した情報を開示するものです。
53.「特例開示」は誰でもできますか?
53.債権者、債務者、電子記録保証人、対象となるでんさいの債権記録に記録されている者およびその相続人ならびにこれらの者の財産の管理および処分をする権利を有する者に限ります。
54.開示請求を行う権利があるのは、誰ですか?
54.現在の利用者、利用者の相続人、利用解約後の元利用者です。
55.債権照会(開示)とは、何ですか?
55.発生記録請求を行った電子記録債権や保有している電子記録債権等の債権照会(開示請求)ができます。開示請求により債権内容が確認できます。
56.「でんさい」の支払方法を教えてください。
56.口座間送金決済による支払いが原則です。
支払期日になると自動的に送金されるため、振込手続、取立手続のような面倒な手続きは一切不要です。
57.決済予定の連絡はありますか?
57.支払期日の2営業日前に「決済予定情報」が電子メールで通知されます。
58.支払期日を迎えた保有債権の資金はいつから利用できますか?
58.支払期日から利用可能です。
原則として支払期日中に債権者側の口座に入金され、支払期日からご利用いただけます。- ただし、入金時刻は債務者の資金準備状況によって異なります。
59.支払期日の口座間送金決済は利用者の口座に何時に入金となりますか?
59.入金時刻は債務者の資金準備状況によって異なります。
なお詳細につきましては、お取引店にご確認いただくようお願い致します。
60.債務者ですが、口座間送金決済のための決済資金は、いつまでに決済口座に準備する必要がありますか?
60.支払期日当日の円滑な手続のため、支払期日の前日までに決済口座への入金をお願いします。
61.「でんさい」を発行した債務者ですが、支払期日に口座引落されましたが、通帳にはどのように表示されますか?
61.以下となります。
通帳摘要欄は、12桁で『D + 電子記録債権番号の下11桁』となります。
62.「でんさい」を保有していますが、支払期日に口座間送金で決済口座に入金されますが、通帳にはどのように表示されますか?
62.以下となります。
通帳摘要欄の表記は、12桁で『D + スペース(1桁) + 支払人(カナ氏名)』となります。
63.債務者ですが、支払い期日に残高不足のため引落しできなかった場合、どうなりますか?
63.手形の不渡りと同じような支払不能制度があります。
期日に入金できなかった場合には、支払不能通知を送信致します。
2回目の支払が不能になった場合は、取引停止となり、電子記録債権の債務者利用と金融機関からの新規借入が2年間制限されます。
64.支払等記録では、どのような請求ができますか?
64.口座間送金決済以外の方法で決済された場合、支払等記録請求を行うことができます。
※通常は口座間送金での決済となり、送金と同時に記録請求されますので、あらためての支払等記録の請求は不要です。
支払等記録請求には、債務者または保証人として「支払を行ったことによる記録請求」と債権者として「支払を受けたことによる記録請求」があります。
「支払を行ったことによる記録請求」の場合は、相手方が承諾することで支払等記録が成立しますが、「支払を受けたことによる記録請求」の場合は、単独で記録が成立します。(相手方の承諾回答は不要です)
65.債務者ですが、支払期日に口座間送金決済で支払をしましたが、支払等記録が記録されていません。いつ支払等記録は記録されるのでしょうか?
65.支払等記録は、支払期日の3銀行営業日後に行われます。
※通常は口座間送金での決済となり、送金と同時に記録請求されますので、あらためての支払等記録の請求は不要です。
支払期日に口座間送金決済が行われたでんさいに対する支払等記録は、支払期日の3銀行営業日後に行われます。なお、口座間送金決済が行われなかった、でんさいに対する支払不能登録についても、支払期日の3銀行営業日後に行われます。
66.支払不能処分制度とは、何ですか?
66.でんさい取引の安全を確保するためにでんさいネットが設けた制度であり、主な内容は以下のとおりです。
- 支払期日にでんさいの支払が行われなかった場合(支払不能)、このでんさいの債務者について支払不能が生じた旨およびその事由が全参加金融機関に通知されます。(ただし、債務者の信用に関しない支払不能(第0号支払不能事由)を除く)
- 同一の債務者について、支払不能が6か月以内に2回以上生じた場合(ただし、第0号支払不能事由の場合を除く)、その旨が全参加金融機関に通知されるとともに、債務者に取引停止処分というペナルティーが科されます。
- 債務者は、一定の条件を満たした場合、異議申立により取引停止処分の猶予を受けることができます。
67.取引停止処分とは、何ですか?
67.債務者が6か月以内に2回以上支払不能でんさいを生じさせた場合に、当該債務者に対して①債務者としてのでんさいネットの利用、②参加金融機関との間の貸出取引を2年間禁止するものです。
手形の取引停止処分に類似の制度であり、この取引停止処分を科す旨の通知は、全ての参加金融機関に対して通知されます。
68.取引先管理とは、何ですか?
68.得意先などのよく取引を行う相手方の情報をあらかじめ登録し、またその情報の変更や削除、照会を行うための機能です。
69.指定許可管理とは、何ですか?
69.特定の取引先(利用者)からのみ記録請求を受け付けることができる機能です。
発生記録(債務者請求方式)、発生記録(債権者請求方式)、譲渡記録、保証記録(単独) の指定が行えます。
- 【発生記録(債務者請求方式)を指定した場合】
- 特定の利用者(債務者)からの発生記録請求のみ受け付けられます。
- 【発生記録(債権者請求方式)を指定した場合】
- 特定の利用者(債権者)からの発生記録請求のみ受け付けられます。
- 【譲渡記録を指定した場合】
- 特定の利用者(譲渡人)からの譲渡記録請求のみ受け付けられます。
- 【保証記録(単独)を指定した場合】
- 特定の利用者(債権者)からの保証記録請求のみ受け付けられます。
70.債権発生請求において、相手先に手数料を負担してもらうことができますか。
70.可能です。ただし、債権発生請求(債務者請求)のみのご利用となりますので、債権発生請求(債権者請求)や譲渡記録請求ではご利用できませんのでご注意ください。
手数料を相手先負担とする場合は、先方のお取引先とご相談の上、ご利用ください。
71.残高証明書を発行してもらうことができますか。
71.可能です。残高証明書の発行方式には、過去日付を基準日とする「残高証明書(都度発行方式)」、未来日付の基準日で定例的(毎年・毎月等)に発行する場合や基準日のみに発行する「残高証明書(定例発行方式)」の2通りの方式があります。方式によって発行手数料が違いますので、ご注意ください。
諸届け
1.社名変更・住所変更・改印等をしたいが、どのような手続きが必要ですか?
1.取引店にてお申し出いただければ、法人ダイレクトの手続きの必要ありません。
手続きについての詳細は、お取引店にお問い合わせください。
※なお、社名変更の場合、法人ダイレクトに反映するまで1週間程度かかりますのでご了承ください。
問い合わせについて
1.操作はどこに問い合わせすればよいですか
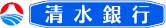

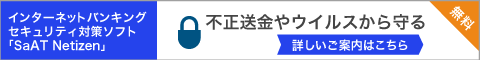
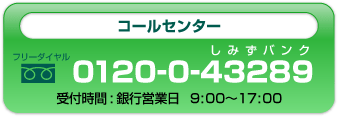
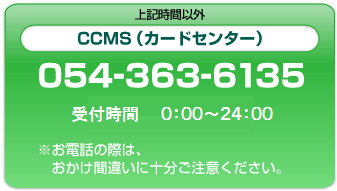
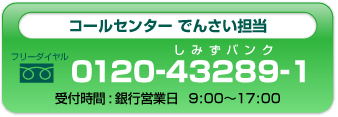
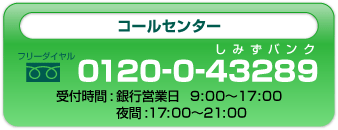
 店舗・ATM
店舗・ATM 手数料一覧
手数料一覧 金利情報
金利情報 資料請求
資料請求 Q&A
Q&A お問い合わせ
お問い合わせ